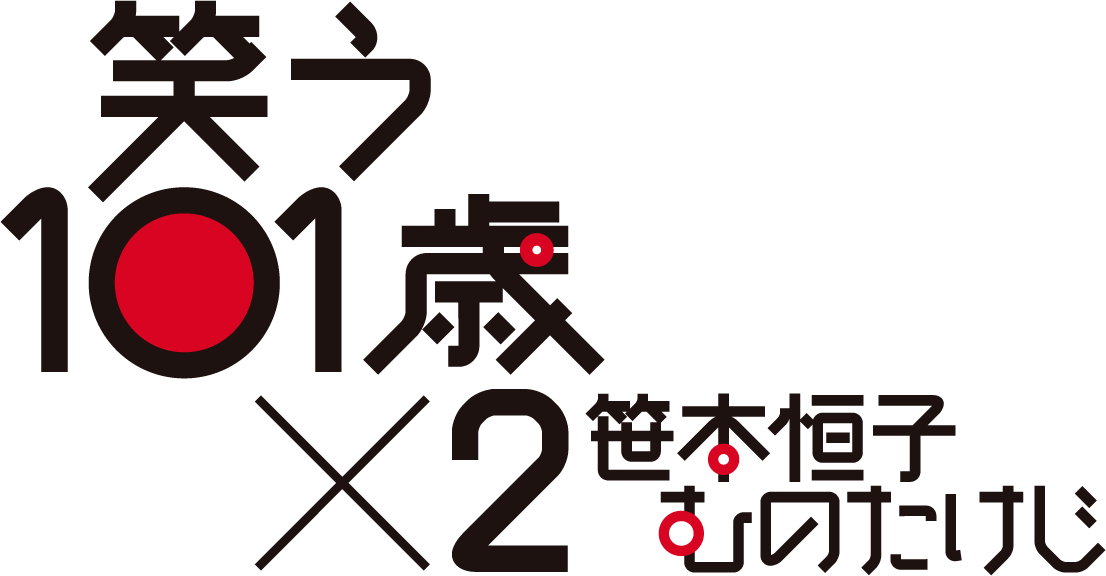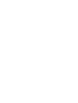河邑厚徳 監督インタビュー
日本の現代史を骨に、
ふたりの人間の100年を描きたかった
――本作を撮ることになったきっかけを教えてください。
2014年4月、横浜でむのたけじさんと笹本恒子さんの100歳対談が行われることを知りました。以前から興味は持っていましたが、お二人とも会ったことはなかったんです。その時点で映画にすることは念頭にありませんでしたが、何か面白いことが起きそうだという予感があり、まずはカメラに収めておきたいと思いました。
ちょうど、前作の「大津波・3.11未来への記憶」を撮り終わり、編集に入ったころ。津波というのは、100年や1000年の時間規模で起きてくる大災害です。東北を歩いていると、昭和の始めに起きたの大津波の話などが必ず出てくる。そういうことから、“100年の歳月ってどんなものだろう"という意識が生まれていたのも事実です。
ジグゾーパズルのようにバラバラな断片が組み合わされ、ひとつの画面が出来上がります。その結果を想像してワクワクする時間が始まるのです。僕の場合、ドキュメンタリー企画のはじまりはそこから。最初から全体像が見えているわけじゃないんですよ。
といっても、その対談は2台のカメラで押さえています。せっかくの機会なのでしっかり撮影したかったからです。この二人については、いつでもラストチャンスだと思わなければいけないという気構えが当初からあった。結果的に、あの日が最初で最後のツーショット、とても大事なシーンとなりました。
――むのさんと笹本さんの第一印象はいかがでしたか。
むのさんは、見た目は等身大の老人なのに、いざ質問を始めると本当に情熱的に語り出します。まずはそのギャップに驚きました。この人は「骨董品」だと思いました。時代が磨き上げた美しさがあり、たくさんの手に触れて、その物しか持ち得ないかけがえのない佇まいがある。
骨董品って、一見ぼろぼろの古びたものに見えるでしょう? むのさんも喋る前はぼろぼろのおじいさんに見えた。ところがいったん喋り始めると、骨董のお茶碗にお抹茶を立てたように、普通ではあり得ない美しさや味わいが出てくるんです。侘び寂びとも少し違う。僕はむのさんのことを国宝級の骨董品だと思いました。
笹本さんは、むのさんの印象とはまったく違っていて、僕にとって謎。ミステリアスです。撮影のたびにいろいろなことを話してくださるけれど、どこか腑に落ちない。たとえば彼女は、テレビや雑誌などでずいぶん取材を受けていますが、相手によって見せる顔が微妙に違います。同じことを言っているようでも違うんですよ。
日本初の女性報道写真家という肩書はあっても、長い人生の間には絵を描き、洋裁やフラワーデザインをしたり、アクセサリーを作ったり、常に変身を繰り返している。出逢いによって変態する「メタモルフォーゼ」と言ったらよいかもしれません。これは女性というものが持っている謎だろうか。その謎を解いていく面白さが、笹本さんの主題となりました。
二人に共通しているのは、すさまじい記憶力。自分が会った人たちの名前や年号、空気感や感覚などのディテールまで、それぞれの頭にインプットされているんです。おそらく誰でもそういう記憶は自分の頭に入っているのですが、すぐに引き出すことは難しい。人の名前が出てこなくて半日くらい悩んでしまう僕のような凡人からすると、「すごい!」と思わずにはいられませんでした。
――そこから撮影がスタートしていくのですね。
戦後70年が間近だったので、むのさんについては対談の後すぐに撮影を始め、月2回ペースで会いに行きました。彼は第1次大戦の翌年に生まれ、戦中戦後を走り続け、現代まで現役でジャーナリストとしてものを見てきている。そんな人はレア中のレア、唯一無二の存在です。日本の社会から確実に絶滅していく存在だから、記録しなければという意識が働きました。
むのさんは戦後、朝日新聞をやめて、故郷の秋田県横手市で「たいまつ」という週刊新聞を立ち上げます。たいまつというのは火を灯して掲げるトーチ。僕はそれをバトンだと感じ、次世代へ、さらに次の世代に手渡していくイメージが生まれた。そのトップランナーであるむのさんを、なんとかものにしたいと取材を続けました。そして、むのさんの思想や体験を伝えるテレビ番組(ETV特集)を戦後70年の夏に作り、非常に大きな反響を得られました。
一方で、横浜での対談が終わったときには、最終的なゴールとして二人を主人公にした映画にしたいと思いました。まだ何も決まっていないし、うまくいくかはわからないけれど、自分の目標、夢になっていたんです。
あの二人は、私たちには見えない風景――ビルの101階からの風景が見えている。つまり、時空間をビルに例えて、1階2階3階、そして20階、60階、101階と積み重なった階からの風景を俯瞰しているということです。そして、この激動の100年をリアルに体験している。時間と空間で100という数を体験している人をリスペクトするのと同時に、それはどういうことなのだろうかということが切り口のひとつになると思いました。
笹本さんの撮影は横浜の対談の半年後、9月1日の彼女の100歳の誕生日からスタートしました。回したビデオテープは二人合わせて150時間ほどになります。ただ、先ほども言ったように、笹本さんのことはなかなか核心がつかめず、編集ぎりぎりの段階までカメラを回しました。
――撮り続けていくうちに、見えなかった本質にたどり着いたのですか。
笹本さんについては、彼女がライフワークとしてきた「明治の女性たち」に焦点を当てました。写真家として明治の女性を追いかける問題意識が、彼女自身の人生と重なっていったんです。被写体の多くは男性遍歴があり、最後まで女性として生き抜いた人。宇野千代さんや三岸節子さんなど、100歳近くまで生きた女性も何人かいますが、みんな色っぽい話が最後までつきまとうんですよ。
女性と男性が不平等な時代に頑張ってきたというきれいごとではなく、その人たちの生身の人生に向き合うことで、自分自身が励まされたり癒されたりするから、笹本さんは仕事を続けてこれたんだと思います。
むのさんは、「80年ジャーナリスト一本道」という言い方を自分でもしていますが、まったく変節せず、ぶれずにジャーナリストを貫いてきました。
フリーランスで組織に属さないという意味で、二人は共通しています。大上段に掲げてものを言うマスメディアとは一線を画し、日本独特の狭い価値観からは距離を置き続けている。むのさんは反戦主義の左翼文化人と称されることもあり、ガチガチに頭が固いと思われるかもしれませんが、実際はまったく違います。きわめてリベラルだし柔軟で、いつも人びとの日常に寄り添ったものの見方をしているんですね。
そういう意味では、むのさんと笹本さんは同じ目線を持っています。二人ともどこかあどけないところがあり、永遠の少年少女でもある。権威主義ではないし、他人に道徳やモラルを説く人でもない。非常に稀有な存在だと思います。
――「笑う101歳×2」というタイトルはどうしてついたのですか?
映画にしようとした時点で、僕の中でのタイトルは「100歳×2」に決まっていました。あの横浜の対談では、二人して豪快に笑っている。年をとるにしたがい表情がなくなっていく人も多いのですが、彼らは本当によく笑うんですね。ですから「笑う」という言葉も、撮影しているうちに自然に思いつきました。
101歳の誕生日にむのさんのお宅にうかがったとき、息子の大策さんと二人で「死に方の練習をしよう」と話していたんですよ。「笑いながら死ぬことは誰もやっていない。だから笑って死ぬんだ」という話を親子で何度もしているのがおかしくて。すでにこのタイトルを思いついていましたが、「やっぱり正解だったな」と思えました。
このタイトルには、映画を観た人が微笑みながら映画館を出られるようにという思いもこめています。シリアスなシーンもありますが、むしろ笑ってほしいなと思う。
今の世の中は、閉塞状況で先が見えないし、窮屈だし、嫌なことがいっぱいあるでしょう。でも、むのさんと笹本さんの二人が、100年を超えてこういう生き方をしたということが励ましになってほしいなと思いました。ワッハッハという爆笑ではなく、ふっと笑えるように。
そして、むのさんが自宅で最期を迎えるラストカットは、時代の目撃者むのたけじの目、その見据える先を、観る側そして次世代に考えてほしいと思いました。その先にあるのは悲観ではなく微笑み、希望であってほしいと思います。
――映画に流れる音楽とナレーションが、大きな役割を果たしていると思います。
音楽の加古隆さんは、NHK「映像の世紀」のイメージが強くありました。この映画も100年の歴史があるわけですが、加古さんの音楽は、時間を回顧するという部分を、うまく伝えてくれるという思いがあってお願いしました。
加古さんは映像を単に見るだけでなく、インタビューなどもじっくり聞いて、そこから音楽の構想を練っていくんです。こんな深いところまで見てくださっているんだなあと感じたのは、むのさんが、朝鮮半島から来た飴売りの人たちに子どもながらシンパシーを感じていたというシーン。「差別する気持ちはまったくなかった。私は東北だから」と言いますね。その言葉に加古さんはいたく納得され、東北が差別され続けた地域だということを感じられたようでした。お忙しいのに丁寧に時間を割いて、この作品を一緒に仕上げてくださいました。
ナレーションの谷原章介さんは、非常に表現力のある方です。今回は男性の物語と女性の物語が複層するため、むのたけじを語る語り口と、笹本恒子を語る語り口はちょっとニュアンスを変えたかった。男性と女性、別々のナレーションでいこうかとも考えましたが、前々作『天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ"』のときの谷原さんの表現力と語り口を思い出し、ぜひ今回もやっていただきたいとお願いしました。
どちらかというと中性的で、気持ちに寄り添ってくれる声質なので、二人の物語を紡いでいくナレーターとしてこれ以上の人はいなかったと感じています。
――今後、日本は超高齢社会に突入していきます。
これからは、当たり前に100歳まで生きる時代が来る。日本は世界的にも先頭を切っているといわれます。今まで高齢者の定義は65歳以上でしたが、元気な老人が増えているため、75歳以上に見直す提言も行われています。
そんななか目にしたのが『LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略』(リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著/東洋経済新報社)という本です。大学を出て、会社に就職して、定年まで勤めて、引退後がある……という従来のコンセプトではない人生。時代時代によって、まったく新しいステージで新しいことを始めていく、変化できる人が元気で100歳を超えていくというくだりが印象的でした。
そういう意味では二人とも顕著です。むのさんは報知新聞、朝日新聞の記者から、戦後はたいまつを作って、その後は文筆と講演にシフトしながらも、最期までジャーナリストを貫いた。笹本さんも画家志望だった少女が報道写真家になったかと思うと、ある時はオーダーサロンを開き、フラワーデザインをしたりアクセサリーを作ったりして、70歳を越えて再びカメラを持ち始める。変化していく生き方が人の命を活性化させ、遺伝子を刺激して、寿命能力にスイッチオンするんですね。
「変節せず、ブレることなく生きた」むのたけじ。「とらわれず、適応しながら生き抜く」笹本恒子。ひとつを貫くむのさんの生き方も、笹本さんの変化し続ける生き方も、どちらもしなやかでカッコいい。この映画が人生100年時代を生きるヒントになればよいと思います。
(インタビュー構成・菅 聖子)